Basic Knowledge
基礎知識
サービスに関する関する基礎知識をわかりやすくまとめています。
Inheritance Procedures
相続手続き
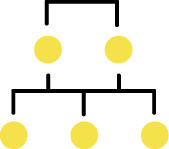
-
相続は、人の一生の中で避けては通れない非常に重要な問題です。財産がたくさんある人もそうでない人も、死亡すれば相続は必ず開始します。それだけに、関心は大きいのですが、その割に基本的なことが分からない、知らない、誤って理解しているということが多いようです。
相続とは、人が死亡したときに、その死亡した人(被相続人)が生前に有していた財産に関する一切の権利義務をその相続人が継承することをいいます。
したがって、原則として、不動産や現金などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産も相続の対象になります。なお、相続財産とはならないものもあるので、注意が必要です。
-

Will Preparation
遺言書作成
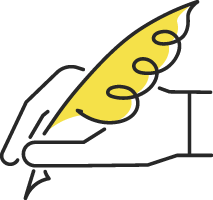
-
日本の高齢社会を背景に、遺産分割をめぐる相続人同士の紛争が急増しています。自分の配偶者や子供などの間で相続が争族にならないように、予防策を採っておくことは今後財産を残す者にとって非常に重要なことになります。
遺言は、遺言者の最終意思を死後に実現することができると同時に、予想される争いを未然に防止する機能を果たしてくれるのです。相続人の異論を封じ遺言としての効力を生じせしめるためには、法に定める方式に従わなければなりません。
また、子供がいない方、おひとりさまの方は、特に、最終意思を示したしっかりとした遺言書を残しておくことは欠かせません。
-
遺言は、15歳以上の者であれば自由にすることができます。その効力が遺言者の死亡後に生じるものであるために、厳格な要件が法定されており、その要件が欠けたものは、せっかく遺言として残しても効力が認められません。
遺言の方式には普通方式と特別方式とがありますが、ほとんどのケースで普通方式の公正証書遺言もしくは自筆証書遺言が利用されます。
-
公正証書遺言
遺言者本人の口述に基づき公証人が遺言書を作成する方法です。公証人が遺言書の口述を筆記し、これを遺言者及び2人の証人に読み聞かせ又は閲覧させます。その筆記が正確なことを確認したあと遺言者、証人が各自署名、押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。的確で完全な遺言書を作成できる代わりにそれなりの費用が必要となります。公正証書遺言は、費用はかかりますが、最も安全で確実な方式といえます。
※原本は証書作成後140年間、公証役場に保管されます。 -
自筆証書遺言
遺言者が自分で筆をとり、財産目録等を除く遺言の本文、日付を自書し、署名、押印することによって作成する方法です。それぞれの要件は非常に厳格で小さな記述ミスで効力が否定されることがあるので注意が必要です。筆記用具や用紙には特に制限はありません。作成のための手続も特にありませんが遺言者の死後、遺言執行のために原則として裁判所の検認手続が必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管制度が始まり、利用すれば家庭裁判所の検認は不要です。
-
-
-
公正証書遺言
【 メリット 】
- 形式の不備がないので無効の危険性がほぼない
- 偽装、変造、紛失の恐れがない
- 検認手続の必要がない
【 デメリット 】
- 遺言作成の事実や内容を秘密にできない
- 作成の手続が面倒・作成費用がかかる
-
自筆証書遺言
【 メリット 】
- 誰にも知られず書ける
- いつでも書くことができ、作り直しも簡単にできる
- 費用が殆どかからない
【 デメリット 】
- 形式などの不備による無効の危険がありトラブルの原因になりやすい
- 偽造、変造、紛失の恐れがある
- 原則として検認手続が必要
-
Adult Guardianship
成年後見
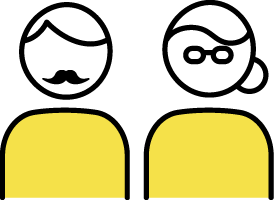
-
認知症などの精神上の障がいにより物事の判断ができなくなった方のために財産管理や契約締結などの支援を行う制度です。成年後見制度には任意後見契約と法定後見があります。
-
自分が元気なうちに将来自分に代わり財産管理などをしてくれる人物を決め、公正証書で契約を交わしておきます。判断能力の低下後、その人(任意後見人)に契約にしたがったサポートをしてもらう制度です。当人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
-
家庭裁判所が関係者からの申し立てに基づき、判断能力が十分でない方に後見人等を選任します。本人に代わり財産管理や契約締結など行う後見人は、家庭裁判所が決定します。法定後見には3つの段階(類型)があり、医師の診断によって決まります。
- 補助
- 本人の判断能力が不十分である
- 保佐
- 本人の判断能力が著しく不十分である
- 後見
- 本人の判断能力が全くない
本人の能力が衰え自分では正しい判断ができなくなると、日常生活に支障がでることも多くあります。後見人を選任することで本人に代わり財産管理や契約締結が行われ、本人の生活が保護されます。 当人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
Legal Planning
備えの法務

-
おひとりさま、おひとりさま予備軍が増加しています。2040年の生涯未婚率は、男性30.4%、女性22.2%と推計されており(2024年推計)、独身者の方が、この先も“おひとりさま”の可能性は決して低くありません。ご夫婦であっても、死別・離別による“おひとりさま”ということもあります。
人生100年時代!おひとりさまは、もはや他人事ではありません!
さらに、将来、介護や支援が必要な人の割合は、80歳代前半で約3割、85歳以降は約6割というデータがあります(2023年9月現在)。誰かに頼ることになるという現実を受け止め、人生設計をすることが大切です。今まで何も想定していなかった方も漠然とした不安を抱えていた方もおひとりさまの将来の備えが待ったなしなのです。
-
見守り契約とは、身寄りや頼る人がない高齢者などとの間で定期的な訪問や電話連絡を行い、本人の生活状況および健康状態を把握して見守ることを目的とする契約です。暮らしの上での心配事や困りごとについて助言を受けることもできます。
見守り契約は、財産管理委任契約や任意後見契約と同時に結んでおくことで、必要な時に、スムーズに安心して各契約へ移行できるようにするための役割があります。
また、遺言書作成時に、いざという時に備え、契約するような場合もあります。 見守りといえば、民生委員が思い浮かびますが、民生委員の方が高齢化していたり、法律に詳しくないことがありますので、連携・役割分担することもひとつです。 当人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
-
財産管理委任契約とは、お身体が不自由な高齢者や障がい者のため、行政書士等の信用できる第三者が、本人に代わって財産を管理し、継続的に支援していくための契約です。具体的な開始時期や内容は、自由に決めることができます。
高齢者の方は、元気なうちに、障がい者の方は、親などの援助者がご健在のうちに、財産管理を委託することで、高齢者ご本人の財産を保護することができ、障害を持つ子どものために財産を有効に活用することができます。さらに、専門家の第三者が入ることで悪徳商法からの被害を防ぎ、親族からの経済的虐待から守ることもできます。
成年後見制度の任意後見契約が「判断能力が低下したとき」に備えるものなのに対し、財産管理委任契約は「判断能力はあるけれども、身体の自由がきかない場合」などに利用できます。将来に備えて任意後見契約を結ぶ場合は、「財産管理委任契約」をセットで結んでおかれることをお勧めします。
-
死後事務委任契約とは、亡くなってしまった、その後が心配な方のために葬儀、遺品整理、役所への届出などの死後の手続を生前に第三者に委託しておく契約です。訃報を知らせたい人、葬儀内容や埋葬方法を詳しく決めておくこともできます。
生前に葬儀会社と契約し、希望の葬儀内容を決めておくと、さらに安心でしょう。なお、死後事務委任契約では、財産の分割や遺贈は、決めることができません。また、亡くなった後の預貯金や不動産を動かすこともできません。そのようなことは、遺言書で決める必要があります。